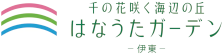LGBTQカップルの終活の悩み|解決に役立つ制度や新しい供養の形

LGBTQカップルが終活を進める際、直面する課題は数多くあります。
法整備は進んでいるものの、とくに終活の場面ではLGBTQカップルが十分なサポートを受けられているとは言えないのが現状です。
本記事では、LGBTQカップルが直面する終活の悩みと解決するための方法・制度、近年おすすめである新しい供養方法についてご紹介します。
LGBTQカップルが終活で直面する主な悩み

LGBTQカップルが終活を始めると、法律や慣習に基づく不平等に直面することが少なくありません。
近年では200以上の自治体が導入している「パートナーシップ制度」や、名古屋市・大阪市などで始まった「ファミリーシップ制度」など、生前のLGBTQカップルを支援しようという取り組みは広がっているものの、終活の場面にまでは行き届いていません。
以下では、そんなLGBTQカップルが直面する代表的な終活の悩みを3つに絞ってご紹介します。
お墓
LGBTQカップルが直面する一つ目の大きな悩みは、お墓の問題です。
LGBTQカップルであっても、法的にはパートナーと同じお墓に入ることができます。
しかし、実際は同性のパートナーが先祖代々のお墓に入ることを、家族(祭祀主宰者)が拒否し、一緒のお墓に入ることができない場合も多いです。
婚姻関係にある夫婦であれば、どちらかが亡くなった後に一方のお墓に入ることは珍しくありませんが、LGBTQカップルというだけで拒否されることがあります。
また、LGBTQカップルが自分たちでお墓を購入しようとした場合には、霊園の規定で同性パートナーは一緒の墓に入れないことになっており、断られる場合もあります。
この他にも、継承者がいないことを理由にお墓の購入を断られるケースもあり、LGBTQカップルがお墓を用意するには多くの障壁があります。
相続
次に、相続の問題があります。
民法上、配偶者でない限りパートナーは法定相続人として認められません。
しかし、LGBTQカップルは法的には結婚していないため、配偶者になることができず、パートナーが亡くなったときに遺産を相続できないのです。
これにより、パートナーが亡くなった後、残された方が経済的に困窮してしまうケースも少なくないのです。
また、遺族とパートナーが遺産を巡ってトラブルになることもあります。
葬儀
LGBTQカップルにとって、葬儀の問題も重要な悩みです。
例えば、パートナー家族に自分がLGBTQであることを伝えていない場合、亡くなった後に葬儀に参列できないことがあります。
参列できた場合でも、喪主として葬儀を取り仕切ることができず、一般参列者として葬儀に参加せざるを得ないケースも少なくありません。
長年苦楽を共にしてきた家族として最後の見送りをしたいと考えている方も多くいるでしょう。
LGBTQカップルの終活に利用できる制度

LGBTQカップルが直面するこれらの悩みを解決するために、利用できる制度はあります。
以下では、いくつかの制度とその注意点をご紹介します。
遺言
遺言書を作成することは、LGBTQカップルにとって非常に有効な手段です。
遺言を残すことで、婚姻関係にないパートナーにも遺産を相続させることが可能になります。
遺言がない場合、民法に基づき法定相続人に財産が配分されるため、パートナー名義の家に住んでいても、相続後に追い出されるリスクが生じます。
また、遺言書には、パートナーに葬儀の喪主を任せることも記載できます。
ただし結婚していない場合、相続税が高くなってしまうことがあります。
一部の控除や特例が適用されないため、税金面での負担を考慮しなければなりません。
養子縁組
養子縁組は、2人の間で戸籍上の親子関係を作る制度です。
これは同性、異性を問わず適用可能で、必ず年上の方が親、年下の方が子となります。
LGBTQカップルが養子縁組を行うことで、一般的な親子に認められるさまざまな法的権利を得られます。
例えば、相続権や遺族年金の受給権、緊急時の医療行為の同意権などが挙げられます。
同じ苗字を名乗り、同じ戸籍に入ることも可能です。
ただし、あくまで親子関係を作る制度のため、注意点もあります。
具体的には、パートナーの関係を解消することになり、同時に養子縁組を解消しても、夫婦関係で認められるような財産分与や慰謝料の請求はできません。
また、今後法改正により同性婚が認められた場合でも、養子縁組を解消して結婚することはできません。
現行制度では、養子縁組を解消した2人が結婚することはできないためです。
任意後見制度
任意後見制度は、事故や認知症などで判断能力を喪失した場合に備え、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
同性パートナーを後見人として指定することもでき、公正証書に残す形で契約します。
LGBTQカップルが任意後見制度を活用することで、万が一の場合でも財産管理や生活契約の代理をパートナーに任せられます。
ただし、医療行為に対する同意権は含まれていない点に注意しましょう。
医療行為に対する同意は基本的に親族にのみ認められています。
なお、例外的に親族がいない場合に限り、病院が同性パートナーに同意を求めるケースもあります。
LGBTQカップルのお墓問題は樹木葬で解決するのがおすすめ

LGBTQカップルのお墓問題に対する有力な解決策の一つは、樹木葬です。
従来の墓地における問題を解決し、LGBTQカップルが一緒に眠る場所を確保するために、樹木葬は非常に有効です。
以下で、樹木葬を選ぶことによるメリットをご紹介します。
樹木葬とは?特徴や費用相場、メリット・デメリットまで幅広く解説
2人で一緒のお墓に入ることができる
樹木葬を提供する霊園の多くは、性別や宗教、人種に関係なく、誰でも利用できるように設計されています。
そのため、LGBTQカップルも一緒のお墓に入ることができ、家族からの反対を気にすることなく、亡くなった後も一緒に眠ることが可能です。
もし先祖代々のお墓がある場合でも、分骨によって遺骨の一部を先祖代々のお墓に、残りをパートナーとの樹木葬に納める方法もあります。
生前に一緒にお墓を探すことができる
樹木葬は生前予約が一般的であるため、生前に2人でお墓を探し、予約できます。
これにより、LGBTQカップルは一緒にお墓を選ぶことができ、2人の意向に沿った形で終活を進められます。
また、生前にお墓を選んでおくことで、残された方が困ることなく、安心して供養を行えるのも魅力です。
跡継ぎがいない場合でも安心
樹木葬は、「永代供養」を行っている場合が多いため、跡継ぎがいない場合でも安心して供養を続けられます。
永代供養とは、霊園側が永続的に供養を行ってくれるサービスで、後継者がいない場合でも墓地を守り続けてくれるため、心配することなく安心してお墓を持つことができます。
パートナーが亡くなった後もお墓参りができる
樹木葬を選ぶことで、パートナーが亡くなった後もお墓参りができるのもメリットです。
先祖代々のお墓に入るのを断られてしまった場合でも、しっかりとお墓参りの場所を用意でき、定期的に故人を偲ぶ機会を設けられます。
まとめ
本記事では、LGBTQカップルが直面する終活の悩みと解決するための方法・制度、また、近年おすすめである新しい供養方法についてご紹介しました。
LGBTQカップルに対する支援はさまざまな形で進んでいるものの、終活の面では依然として不平等を感じる機会が多くあります。
とくにお墓の問題は、パートナーの遺族から直接言葉をかけられる機会もあり、精神的なダメージを負うことも少なくありません。
同性のパートナーとのお墓問題にお悩みの場合は、樹木葬がおすすめです。
同性・異性を問わず一緒のお墓に入ることができ、永代供養の霊園であれば継承者の心配もありません。
この機会に一度探してみてはいかがでしょうか。
お知らせ
はなうたガーデン-伊東-では、毎月テーマに沿ってグループ見学会が開催しております。
事前予約制のため、ご希望の方はお電話(0800-555-1187)よりご連絡をお願いいたします。
ご家族・ご友人・おひとりでも、お気軽にご参加ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
※通常の個別見学会も随時予約を受け付けております。
あわせてご検討くださいませ。