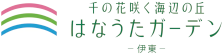家族に負担をかけない永代供養とは?メリットや費用の目安を解説
 「子どもに迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった理由から、近年注目されているのが「永代供養」です。
「子どもに迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった理由から、近年注目されているのが「永代供養」です。
霊園が遺族に代わってお墓の供養・管理を行ってくれるため、無縁仏になる不安がある方や、家族に負担をかけたくないと考える方に選ばれています。
本記事では、永代供養の基礎知識からメリット・デメリット、費用の目安、選び方のポイントまでご紹介していきます。
永代供養とは?
 永代供養とは、霊園や寺院が遺族に代わって、故人の供養や墓地の管理を長期間にわたって継続的に行う供養の形態を指します。
永代供養とは、霊園や寺院が遺族に代わって、故人の供養や墓地の管理を長期間にわたって継続的に行う供養の形態を指します。
後継者がいない方や、子どもや親族にお墓の管理や供養の負担をかけたくない方から注目されており、樹木葬や納骨堂などさまざまなスタイルが選べます。
なお、具体的な内容や期間は霊園や寺院によって異なります。
永代使用との違い
永代供養とよく混同されるのが「永代使用」という言葉です。
永代使用とは、墓地の特定の区画を使用者に永続的に使う権利を与えることを意味します。
つまり、墓地の土地そのものを永久に借りることができる契約形態です。
一方で永代供養は、霊園や寺院がその区画の管理や供養を代行する仕組みであり、使用者本人や遺族が直接管理を行うわけではありません。
このため、「永代」という言葉は似ていても、内容や責任の所在が大きく異なるため注意が必要です。
永代供養にお布施は必要?
永代供養の契約時に支払う永代供養料には、基本的に日常の供養や墓地の清掃、管理費用が含まれています。
しかし、年忌法要や特別な供養を希望する場合は、別途お布施が必要になるケースが一般的です。
お布施はあくまで僧侶への謝礼であるため、永代供養料とは別に用意が必要となるのです。
契約前には、どの範囲まで永代供養料に含まれているのか、また年忌法要の有無や費用についても確認することが大切です。
永代供養の期間は?
「永代供養」という言葉が示す通り、永遠に供養が続くイメージを持つ方が多いですが、実際には契約内容や霊園によって期間は異なります。
例えば、10年や20年など一定期間のみ個別で供養され、その後はほかの遺骨と一緒に合祀されるタイプもあります。
また、永代にわたり個別で安置・供養されるタイプも存在します。
いずれの場合も、契約時に期間の長さや合祀の有無、合祀後の対応について十分に確認することが重要です。
永代供養のメリット

永代供養を選ぶことで得られる主なメリットをご紹介します。
お墓にかかる費用を抑えられる
永代供養では従来のお墓のような墓石を設置しないタイプも多く、特に樹木葬や合祀型の永代供養墓を選べば初期費用を大幅に抑えられます。
墓石の建立費用や広い区画の購入費用が不要なため、通常のお墓に比べて費用が安く済みます。
その結果、ほかの終活にかける費用を充てたり、子どもや家族により多くの資産を残したりすることが可能です。
コストを抑えつつ、自分の理想に合った供養を実現できる点も人気の理由なのです。
関連記事:樹木葬とは?特徴や費用相場、メリット・デメリットまで幅広く解説
継承者の負担を減らすことができる
永代供養は、霊園や寺院が定期的な清掃や管理を代行するため、継承者が日常的なお墓の手入れや法要の手配を行う必要がありません。
これにより、継承者の精神的な負担だけでなく、経済的な負担も軽減されます。
また、複数の親族間でお墓の管理や費用負担についてのトラブルが起こることも少なくなり、家族間の関係が円滑に保たれるというメリットもあります。
無縁仏にならない
跡継ぎがいない場合や家族にお墓の管理を任せられない場合でも、永代供養では契約に基づき霊園側が責任を持って供養と管理を続けます。
そのため、無縁仏になる心配がなく、遺族がいない場合でも安心して供養を任せられます。
自分の死後のことを考え、残された家族に負担をかけたくない方にとって、永代供養は大きな安心材料となるでしょう。
永代供養を利用する場合の注意点

永代供養は便利で安心できる供養方法ですが、利用する際にはいくつか注意すべきポイントがあります。
後悔しないためにも、事前にしっかり確認し、家族とも話し合うことが大切です。
一定期間経過後に合祀される場合がある
永代供養墓の中には、最初は個別に遺骨を安置するタイプでも、一定期間が経過するとほかの遺骨と一緒に合祀される仕組みのものがあります。
合祀された遺骨は元に戻すことができないため、契約時に供養期間や合祀の有無を必ず確認するようにしましょう。
特に、個別でずっと安置したいという場合は確認が必要不可欠です。
親族と話し合う必要がある
永代供養を選ぶ際には、家族や親族との十分な話し合いが重要です。
特に先祖代々のお墓がある場合、「自分はその墓に入るのが当然」と考える親族も少なくありません。
無断で永代供養に切り替えたり、突然別の場所に納骨したりすると、思わぬトラブルに発展することもあります。
円満に進めるためにも、希望や理由を説明し、理解を得てから手続きを進めましょう。
事前に供養の仕方を確認する必要がある
霊園によっては、お墓参りの自由度に制限がある場合もあります。
例えば、供花や線香の持ち込みが禁止されていることや、訪問可能な日時が限られている場合もあります。
自分が望む供養のスタイルに合致しているかどうか、契約前に必ず確認することが大切です。
永代供養にかかる費用の目安

永代供養の費用は、お墓の種類や形式によって大きく変わります。
例えば、永代供養が多く用いられる樹木葬の場合、費用の相場はおよそ67.8万円です。
一方で、墓石を建てる一般墓に永代供養を付けると、費用は100万円を超えることも少なくありません。
また、合祀墓のように複数の遺骨を同じ場所に納骨するタイプは、費用をさらに抑えられる傾向があります。
これらの違いを理解したうえで、自分や家族の希望に合ったプランを選ぶことが大切です。
出典:【第16回】お墓の消費者全国実態調査(2025年)霊園・墓地・墓石選びの最新動向
永代供養を選ぶ場合に確認すべきポイント
永代供養を選ぶ際には、料金や条件をよく理解したうえで選ぶことが大切です。
確認すべきポイントについてご紹介します。
お墓に入る人数
永代供養の料金は、多くの場合「1人あたり」の設定となっています。
つまり、家族や親族など複数人で利用する場合、人数が増えるほど費用も高くなる可能性があります。
どのくらいの人数まで納骨できるのか、追加で納骨する場合にかかる費用があるかどうかを事前に確認しておきましょう。
それによって、予算をオーバーする心配を減らせます。
宗旨宗派の制限
霊園や寺院によっては、特定の宗旨や宗派に限定して受け入れている場合があります。
特に、寺院のお墓は、仏教徒であることが前提のケースも多いです。
宗旨宗派に関わらず利用できるところも増えていますが、自分の信仰や希望する供養スタイルに対応しているかを必ず調べておきましょう。
維持費の有無と金額
永代供養では、契約時に費用を一括で支払う場合と、年間の管理費が別途かかる場合があります。
年間管理料が発生するかどうか、その金額はいくらか、また管理料が含まれている場合でも具体的にどこまでのサービスが対象になるのかをしっかり確認することが大切です。
管理費が発生しない場合は、契約時の費用に霊園全体の管理費が含まれていることが多いですが、追加費用がかからないか念入りにチェックしておきましょう。
金銭面で納得できるプランを選ぶことで、後々のトラブルや不安を防ぐことができます。
まとめ
本記事では、永代供養の基礎知識からメリット・デメリット、費用の目安、選び方のポイントまでご紹介しました。
永代供養は、家族への負担を軽減しながら安心して眠ることができる、現代に合った供養のかたちです。
「はなうたガーデン-伊東-」では、一代式(埋蔵から20年)と永代式をご用意。
どちらの形式でも霊園が永続的に丁寧な管理を行います。
ご契約者様からいただく運営管理料は霊園全体の運営や管理に充てられるため、使用期間経過後や継承を放棄した場合でも、区画が荒れてしまう心配はありません。
また、当園の方針として合祀は行いませんので、契約期間の経過後も自然の中で安らかに眠り続けることができます。