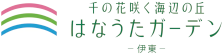お墓の放置によって起きるトラブルは?強制撤去や合祀を防ぐ方法
 お墓を継ぐ人がいなかったり、遠方に住んでいてなかなかお墓参りに行けなかったりなどの事情から、お墓を放置してしまう方が増えています。
お墓を継ぐ人がいなかったり、遠方に住んでいてなかなかお墓参りに行けなかったりなどの事情から、お墓を放置してしまう方が増えています。
長期間放置されたお墓は、管理不全として扱われ、強制撤去されてしまうリスクもあります。
本記事では、お墓の放置によって起きるトラブルや対策、後継者の考え方、そして放置を防ぐ方法についてご紹介していきます。
お墓の放置によって起きるトラブル
 放置されたお墓がどのような流れで撤去・合祀されていくのかを確認していきましょう。
放置されたお墓がどのような流れで撤去・合祀されていくのかを確認していきましょう。
強制撤去され合祀墓に移動される
お墓の維持費や管理料を長期間滞納して放置していると、墓地の管理者から「無縁墓」として扱われる場合があります。
無縁墓とは、継承者やお参りに訪れる人がいないと見なされたお墓のことを指します。
このような状態が続くと、最終的には強制的にお墓が撤去され、遺骨が合祀墓に移されてしまう可能性が高いのです。
ただし、いきなり撤去されるケースは少なく、継承者への通知など段階を追って徐々に手続きが進みます。
継承者のもとへ督促が届く
まず初めに行われるのが、墓地管理者からの督促です。
管理費の支払いが滞ると、郵送や電話などで継承者に対して支払いを促す通知が送られます。
この時点で対応すれば、強制撤去に進むことはありません。
早めの対応が、トラブルを未然に防ぐ第一歩なのです。
官報に氏名が公示される
督促を無視し、対応しない状態がさらに続くと、墓地管理者は法的手続きの一環として利用者の氏名や住所を官報に掲載します。
官報は誰でも閲覧可能であるため、親族や知人にお墓の放置が知られる可能性がある点にも注意が必要です。
お墓が撤去される
官報への公示後もなお連絡・対応がない場合、墓地の管理者は地方自治体の許可を得て、該当のお墓を「無縁墓」として強制撤去します。
墓石は取り壊され、墓地は更地に戻されてしまい、墓所は新たな利用者へ貸し出される可能性もあります。
こうなると、元の状態に戻すことはできません。
遺骨は合祀される
撤去されたお墓に納められていた遺骨は、ほかの無縁墓と共に「合祀墓」と呼ばれる共同の供養墓に埋葬されます。
合祀された遺骨は基本的に個別に取り出すことができないため、家族としても後悔の残る結果となりかねません。
公営墓地では撤去までに時間がかかることが多い
公営墓地や自治体が管理する霊園の場合、お墓の撤去費用にも税金が使われるため、慎重に判断されるケースが多く、即座に撤去されることは少ないでしょう。
しかし、お墓がそのまま残っていたとしても、管理費の請求は続くうえ、放置が長引けば上記の手続きへ進むリスクもあります。
見えないところで着々と撤去準備が進んでしまうこともあるため、早めに対処することが大切です。
お墓の後継者は誰?

お墓の後継者、いわゆる「祭祀継承者」とは、法律上、祖先の供養を引き継ぐ役割を担う人物を指します。
祭祀継承者の決め方は、慣習や被相続人の指定、なければ家庭裁判所の審判などがあり、配偶者・子どもが必ず優先とは限りません。
通常は家族間の話し合いや合意によって決まることが一般的です。
後継者が不明確なままだと、管理費の支払いが滞ったり、供養がされなくなったりして、お墓が放置される原因にもなります。
そのため、自分のお墓を準備する際には、誰がどのように管理・供養していくのか、費用の負担をどうするかまで考えておかなければなりません。
後継者にとって無理のない内容であること、事前に家族としっかり話し合っておくことが、放置リスクを避ける重要なポイントといえるでしょう。
お墓が放置される主な原因

お墓が放置されてしまう背景には、さまざまな社会的・個人的な事情があります。
維持管理の負担が大きい
お墓の維持には、掃除や草取りなどの定期的な手入れに加え、管理費や修繕費などの費用もかかります。
これらが家族にとって大きな負担となることは少なくありません。
近年は経済的な理由で管理費の支払いが難しくなり、結果的に放置せざるを得ないというケースも増えています。
また、代々のお墓を守ってきた世代が高齢になると、管理を引き継ぐ若い世代が負担に感じてしまい、管理が行き届かなくなることもあります。
定期的なお墓参りが難しい
お墓が遠方にあったり、霊園が交通の便の悪い場所にあったりすると、定期的なお墓参りが難しくなります。
特に高齢者の場合、身体的な理由で長距離移動が困難になることも多く、お墓を気にかけていても実際には足を運べない状況が続いてしまいます。
家族が都市部に移り住んでいる場合も、地元の墓地への距離がネックとなり、次第に足が遠のいてしまうことも放置の一因となり得るのです。
お墓を継承する人がいない
少子化や核家族化の影響で、お墓を継ぐ人が見つからないケースも増えています。
かつては長男が家を継ぎ、お墓の管理も担うのが一般的とされていましたが、現代では子どもがいない、または兄弟姉妹それぞれが別の土地で生活しているといった家庭も多く、誰が継ぐかを決められないままお墓が放置されてしまうことがあります。
加えて、遺族同士の関係性が希薄になっている現代では、「誰かが継ぐだろう」と判断を先送りにした結果、誰も手をつけないまま時間が経ってしまうというパターンも見られます。
お墓の存在を知らない
親族と長年没交渉だった場合、自分がそのお墓の祭祀継承者に指名されていたことすら知らず、結果的に放置されてしまうことがあります。
相続や遺産分割の中でお墓についての取り決めが明確でない場合、後継者に情報が伝わらず、誰もお墓の存在を把握していないまま時間が経過してしまうのです。
このようなケースでは、本人が悪意なく放置している状態になるため、事態が発覚したときにはすでに管理費が滞納されていたり、強制撤去が迫っていたりする場合もあります。
お墓の放置を防ぐためにできること

お墓が将来的に放置されるリスクを減らすには、早めの対策が欠かせません。
墓じまいを行う
お墓の維持が難しいと感じたら、まず検討したいのが「墓じまい」です。
墓じまいとは、お墓を撤去し、遺骨を別の場所へ移すことを指します。
放置によるトラブルや管理費の滞納を避ける有効な手段として、近年利用者が増えています。
墓じまいは基本的に以下のような流れで進めます。
1. 親族から同意を得る
2. 墓地の現状(遺骨の数や状態など)を確認
3. 墓地管理者へ墓じまいの申し出を行う
4. 改葬先(永代供養墓など)を決める
5. 複数業者から見積もりを取り、比較する
6. 改葬許可証を取得する
7. 閉眼供養を実施し、遺骨を取り出す
費用面では、墓石撤去費や離檀料、閉眼供養料が必要になる場合があるため、事前に詳細を確認し、親族や菩提寺との十分な話し合いをしておくことが重要です。
関連記事:墓じまいのやり方は?必要な手続きを7つのステップで解説!
永代供養墓へ改葬する
墓じまいを行った後の、遺骨を改葬する先として「永代供養墓」があります。
永代供養墓は、霊園や寺院が責任を持って永続的に供養・管理してくれるため、後継者が不要となり、お墓の放置や無縁墓化を防ぐことができます。
樹木葬など、永代供養タイプのお墓を提供する霊園が近年増えています。
手元供養を行う
もう1つの選択肢としては「手元供養」があります。
手元供養は、墓じまいの後に遺骨をお墓に納めず、自宅で小型の骨壺などに入れて供養を行う方法です。
手元供養であれば、遠方のお墓に通う必要がなく、身近な場所で故人を感じながら供養できるという安心感があります。
まとめ
本記事では、お墓の放置によって起きるトラブルや対策、後継者の考え方、そして放置を防ぐ方法についてご紹介しました。
お墓が放置されることによって、無縁墓化、強制撤去、合祀といった取り返しのつかない事態が起こる可能性があります。
「はなうたガーデン-伊東-」の樹木葬は、オリジナルの紙製骨壺によりゆっくりと土に還っていくため、一般墓のように墓石が放置され無縁墓になる心配がありません。
また、継承者不要のプランもご用意していますので、「お墓を継ぐ人がいない」「子どもや孫に負担をかけたくない」方にも安心してご利用いただけます。