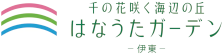樹木葬の手続きはどう進める?改葬を行う場合の流れも解説
 自然に還る新しい供養のかたちとして人気の樹木葬ですが、実施にはさまざまな手続きや準備が必要です。
自然に還る新しい供養のかたちとして人気の樹木葬ですが、実施にはさまざまな手続きや準備が必要です。
特に、先祖代々のお墓がある場合には「改葬」の手続きも必要になるため、流れを把握しておくことが大切です。
本記事では、故人が亡くなってから納骨までの行政手続き、樹木葬の契約・納骨までの流れ、改葬の進め方、さらに失敗しないための注意点についてご紹介していきます。
亡くなってから納骨までに済ませておく行政手続き
 故人が亡くなってから納骨に至るまでには、いくつかの行政手続きを行う必要があります。
故人が亡くなってから納骨に至るまでには、いくつかの行政手続きを行う必要があります。
手続きを正しく進めることで、葬儀や納骨が滞りなく進められますので、事前に流れを把握しておくことが大切です。
以下に、一般的な手順を追ってご紹介します。
1. 死亡診断書・死体検案書を受け取る
まず、医師や警察から死亡を証明する書類を受け取ります。
病院で亡くなった場合、担当医師によって「死亡診断書」が発行されます。
一方で、自宅や外出先で遺体が発見された場合や事故で亡くなった場合、警察の手配によって「死体検案書」が交付されます。
どの書類も後に必要となる死亡届の提出に欠かせない重要書類であるため、大切に保管しておきましょう。
2. 自治体の窓口に死亡届を提出する
次に、市区町村役場の窓口へ、「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出します。
死亡届は、通常家族や葬儀社が記入し、病院から受け取った死亡診断書または死体検案書と一体になって提出されます。
提出が受理されると、「火葬許可証」が交付されます。
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内で、提出先は死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの役所です。
3. 火葬を行い、埋葬許可証を受け取る
通夜・葬儀を終えた後、火葬場にて火葬を行います。
その際に、あらかじめ交付された「火葬許可証」を火葬場に提出します。
火葬が完了すると、火葬許可証には所定の押印がなされ、「埋葬許可証」として返却されます。
この埋葬許可証は、納骨や樹木葬など埋葬を行う際に必ず必要となる書類であり、納骨の際には霊園などの管理者に提出しなければなりません。
樹木葬の契約から納骨までの流れと手続き

樹木葬は、霊園選びから納骨までさまざまな手順を踏む必要があります。
一般的な流れを順にご紹介しましょう。
関連コラム:樹木葬とは?特徴や費用相場、メリット・デメリットまで幅広く解説
1. 霊園の情報を集める
樹木葬を行うには、まず霊園選びが重要です。
霊園ごとに樹木葬のスタイルや管理体制が異なるため、自分や家族の希望に合った場所を見つけることが大切です。
チェックすべきポイントとしては、費用・立地・宗旨宗派の制限・埋葬方法・管理の有無などがあります。
インターネットやパンフレットで比較検討し、気になる霊園があれば資料請求をして詳細を確認しましょう。
最近では、自然豊かな場所にありつつも、アクセスしやすい都市型の霊園も増えています。
2. 霊園を見学する
資料だけではわからない霊園の雰囲気や管理状態を確認するには、現地の見学が必須です。
・樹木や草花の手入れが行き届いているか
・園内の雰囲気が落ち着いているか
・ほかの利用者の様子や職員の対応
など、実際に足を運ぶことで多くのことが見えてきます。
また、事前に予約をすれば担当者が案内してくれるケースも多く、疑問点を直接確認できるのも見学のメリットです。
3. 霊園と契約して使用許可証を受け取る
見学を終えて納得できた霊園が見つかったら、契約に進みます。
契約時には永代使用料や管理費などを支払い、「使用許可証」を受け取ります。
この書類は後の納骨時に必要になるため、大切に保管しておきましょう。
また、契約後は霊園側と相談し、粉骨や納骨の日程調整を行います。
納骨式や読経などの有無も、あらかじめ話し合っておくことをおすすめします。
4. 遺骨を粉骨する
樹木葬では、遺骨を細かく砕いてパウダー状にする「粉骨」が必要となるケースがあります。
粉骨は専用の機械を使う必要があるため、基本的には専門業者に依頼します。
霊園が提携している業者も多いため、紹介してもらうという方法もあります。
5. 納骨する
粉骨が完了したら、いよいよ納骨です。
霊園に「埋葬許可証」を提出し、指定の方法で遺骨を納めます。
多くの霊園ではスタッフの立ち会いのもと静かに埋葬が行われ、希望すれば、読経・献花・お別れの言葉などのセレモニーを行える場合もあります。
納骨が完了すれば、後の供養は霊園側が永代にわたって行ってくれる場合が多く、家族の負担が少ないのも樹木葬の魅力といえるでしょう。
改葬を行う場合の流れと手続き

樹木葬を希望する方の中には、すでに家族のお墓があり、そちらから遺骨を移す「改葬」が必要になるケースもあります。
改葬は通常の納骨とは異なり、いくつかの書類や手続きを踏まなければなりません。
ここでは、樹木葬に合わせて改葬を行う場合の具体的な流れと必要な手続きをご紹介します。
関連コラム:墓じまいのやり方は?必要な手続きを7つのステップで解説!
1. 霊園を決め受入証明書を受け取る
まずは、新たに納骨を行う霊園を決めるところから始まります。
霊園の資料を集め、条件や立地、費用、宗旨宗派の制限の有無などを確認し、実際に見学をして納得のうえで契約を結びます。
契約後に霊園から発行されるのが「受入証明書」です。
これは「この遺骨を受け入れます」という霊園側の証明で、改葬手続きを進めるうえで必要不可欠な書類です。
2. 改葬許可申請書を作成する
次に、「改葬許可申請書」を用意します。
これは現在遺骨が埋葬されている墓地のある自治体で入手できる書類で、自治体の窓口やホームページから取得できます。
申請書には、改葬元の情報、改葬先の霊園情報、申請者の署名など必要事項を記入します。
内容に不備があると許可が下りないため、正確に記入することが重要です。
3. 現在利用している霊園の管理者に改葬を相談する
改葬を行う前に現在利用している霊園の管理者に相談し、必要な手続きや日程調整、遺骨の取り出し方法などについて確認しておきましょう。
また、管理者からは遺骨が埋葬されていたことを証明する書類である「埋蔵証明書 」を発行してもらいます。
なお、お寺の墓地で檀家として供養を受けていた場合、改葬にともない「離檀料」が発生することがあります。
4. 自治体の窓口で改葬手続きを行う
最後に、受入証明書・埋蔵証明書 ・改葬許可申請書の3点を持参し、現在の墓地がある自治体へ提出し、改葬手続きを行います。
内容に問題がなければ、「改葬許可証」が交付され、遺骨の移動が正式に許可されます。
その後は新しい霊園で樹木葬の納骨を行い、自然の中で静かに供養できます。
樹木葬の手続きで失敗しないための注意点

最後に、樹木葬の手続きで失敗しないための注意点をご紹介します。
家族や親族と事前に相談しておく
樹木葬に限らず、お墓を選ぶ際は家族・親族間での認識の違いや反対意見が生じることもあります。
そのため、契約前にしっかり話し合い、同意を得ておくことがトラブルを防ぐポイントといえるでしょう。
必ず現地を訪れる
資料だけで判断せず、必ず霊園を実際に訪れて現地の様子を確認しましょう。
草花や木々の管理状況、雰囲気、アクセスのしやすさなども見学時に確認しておくことで、家族全員が納得した上で故人を供養できます。
まとめ
本記事では、故人が亡くなってから納骨までの行政手続き、樹木葬の契約・納骨までの流れ、改葬の進め方、さらに失敗しないための注意点についてご紹介しました。
樹木葬は、自然と共に眠る新しい供養のかたちとして注目を集めていますが、納骨までには行政手続きや霊園との契約、場合によっては改葬の手続きが必要となります。
樹木葬霊園をお探しの場合は、「はなうたガーデン-伊東-」をご利用ください。
ご契約者様それぞれに専用区画をご用意していますので、他の方と合祀される心配がなく、安心して供養ができます。
園内には140種類以上の草花が咲く美しいガーデンが広がり、特別仕様の紙製骨壺を使用することで、自然と共に眠るという樹木葬本来のかたちを実現していただけます。