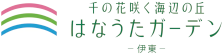お寺での樹木葬は檀家になる必要がある?改葬手続きの流れも解説
 近年、樹木葬を選ぶ方が増えていますが、「お寺に供養をお願いする場合は檀家になる必要がある」と聞いたことのある方も多いでしょう。
近年、樹木葬を選ぶ方が増えていますが、「お寺に供養をお願いする場合は檀家になる必要がある」と聞いたことのある方も多いでしょう。
そこで本記事では、お寺での樹木葬は檀家になる必要があるのか、墓じまいをして改葬手続きをする際の流れについてもご紹介します。
檀家とは?
 檀家とは、寺院に所属している家のことを指します。
檀家とは、寺院に所属している家のことを指します。
寺院に対して定期的にお布施や寄付を行い、経済的な支援をすることで、寺院の運営や維持を支える役割を持っています。
お墓が寺院にある場合、その家は基本的に檀家である可能性が高く、寺院との関係が長く続くことになります。
檀家になることで、家族は寺院の行事や法要に参加しやすくなるだけでなく、日常的な供養や管理のサポートも受けやすくなります。
また、地域や宗旨宗派によっては、檀家制度を通じて地域コミュニティの一員としての役割も担うことになります。
檀家になるメリット
檀家になることで得られる最大のメリットは、法要や供養を寺院に安心して任せられる点にあります。
葬儀や年忌法要、盆・彼岸などの季節法要の際に、希望の日時でスケジュールを調整しやすく、僧侶の手配も円滑に進められます。
急な法要や忌日法要など、短期間での相談にも柔軟に対応してもらえる寺院も多く、家族にとっては安心材料となるでしょう。
また、お墓の維持管理を任せられる点も大きな魅力です。
墓石や植栽の定期的な清掃、供花・線香の補充、法要に必要な備品の準備などを寺院が担ってくれるため、家族が遠方に住んでいる場合や高齢で定期的なお墓参りが難しい場合でも安心です。
檀家になるデメリット
一方で、檀家になることには一定の負担も伴います。
まず、入檀料や定期的な寄付、離檀料など、経済的な負担が発生します。
それぞれの金額は寺院ごとに異なり、相場も明確には決まっていないため、檀家になる前に必ず確認しておきましょう。
また、寺院での行事や法事の際に檀家として手伝いを求められることがあります。
お寺で樹木葬をする場合、檀家になる必要はある?

お寺で樹木葬を行う場合、必ずしも檀家になる必要はありません。
檀家に加入しなくても、戒名の授与や回忌法要などの供養を受けられるケースが多くあります。
永代供養を前提に、檀家制度に縛られず樹木葬を利用できるお寺も増えてきています。
しかし、一部の寺院では樹木葬を利用する条件として檀家への加入を求められることもあるため注意が必要です。
利用条件や費用、法要の対応可否などを事前に確認し、自分や家族に合ったプランを選択しましょう。
檀家になる場合の流れ
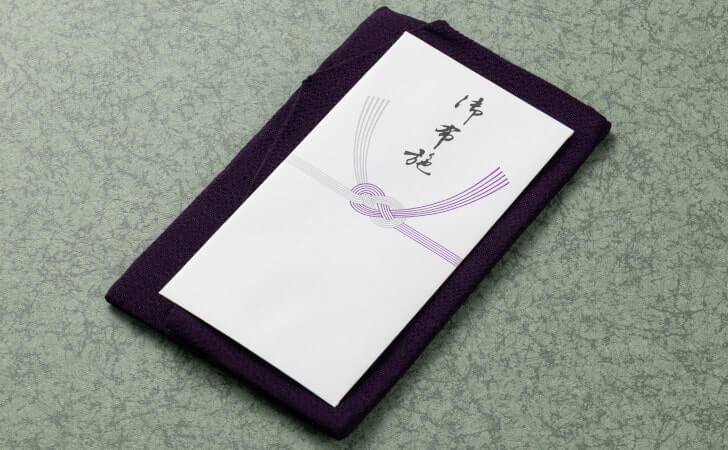
檀家になるには、寺院選びから契約までいくつかのステップがあります。
ここでは、その具体的な流れをご紹介します。
お寺を探す
檀家になる際、まずは信頼できるお寺を探すことが重要です。
葬儀社や親族・知人からの紹介を受けるほか、自分で地域や宗旨宗派に合った寺院を調べるのが一般的です。
歴史や供養の方針を確認し、複数寺院を比較して家族の希望や生活スタイルに合うかを見極めましょう。
見学や相談の際には、スタッフの対応や寺院の雰囲気も確認しておくと安心です。
お寺に相談する
お寺の候補を絞ったら、入檀料や年間のお布施、永代供養の有無、法要や行事への参加義務などを詳しく確認します。
法要の予約はどの程度前から可能か、繁忙期(彼岸・お盆・年末年始)の優先順位、緊急時の連絡体制、メールや電話での相談のしやすさも重要です。
疑問点は遠慮なく質問し、書面や見積で確認していくことで、トラブルの予防につながります。
「檀家契約書」や「墓地契約書」にサイン
条件や費用に納得したら、最後に「檀家契約書」や「墓地契約書」にサインをして、正式に檀家として加入します。
契約後は寺院によるお墓管理や法要、供養サービスを継続的に受けられるようになります。
また、契約書には墓地の使用権の範囲や管理費の支払い方法、お墓を承継する際の流れなど、重要な項目が複数記載されているため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
檀家をやめて霊園で樹木葬をするまでの流れ
 「後継ぎがいない」「将来的にお墓の管理を任せる家族がいない」などの理由で墓じまいを検討する場合、改葬先として樹木葬を選ぶ人も増えています。
「後継ぎがいない」「将来的にお墓の管理を任せる家族がいない」などの理由で墓じまいを検討する場合、改葬先として樹木葬を選ぶ人も増えています。
樹木葬の多くは永代供養に対応しており、後継者がいなくても安心して管理を任せることができます。
ただし、手続きには2ヶ月~半年ほどかかる場合があるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
以下で改葬する際の流れを順に解説します。
1.家族や親せきに相談する
改葬を進める前に、まずは家族や親せきと相談することが大切です。
長年檀家として寺院と関係を構築している場合、家族が何代にもわたってお世話になっている可能性があり、無断で墓じまいをしてしまうとトラブルになるおそれがあります。
寺院に相談する前に、家族や親せきに相談をして理解を得ておくことで、その後の墓じまいや改葬手続きをスムーズに進められます。
離れて暮らす家族がいる場合も、この機会に会いに行くなどして、しっかりと話し合うようにしましょう。
2.樹木葬可能な霊園を探す
次に、樹木葬が可能な霊園を探します。
気になる霊園が見つかったら、現地見学で供養環境や管理体制、スタッフの対応などを確認します。
パンフレットや資料だけでは分からない部分は積極的に質問し、家族も含めて全員が納得したうえで決定しましょう。
契約後には「受入証明書」が発行されます。
受入証明書は改葬手続きの際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。
3.改葬許可申請書を作成する
「改葬許可申請書」とは、遺骨を別の場所に移すことを自治体に認めてもらうための書類を指します。
現在お墓がある自治体の窓口で入手し、必要事項を記入して準備します。
この書類がなければ改葬手続きは進められないため、記入漏れや不備がないよう注意が必要です。
4.寺院に改葬の相談をする
次に、墓じまいの意向を現在お墓がある寺院に伝え、「埋蔵証明書」を発行してもらいます。
檀家としてお世話になっている場合は、離檀料が必要になることがあります。
離檀料の相場は5万~20万円ほどと幅があり 、寺院やお墓の規模によって異なります。
金額や支払い方法については事前にしっかり相談し、納得のうえで手続きを進めることが大切です。
5.自治体で手続きを行う
最後に、自治体の窓口で改葬手続きを行います。
受入証明書、埋蔵証明書、改葬許可申請書を提出し、不備等がなければ「改葬許可証」が発行されます。
これを改葬先の霊園に提出すれば、遺骨の移動が可能になり、豊かな自然の中でゆったりと故人を供養できます。
関連コラム:墓じまいのやり方は?必要な手続きを7つのステップで解説!
まとめ
本記事では、お寺で樹木葬を行う場合の檀家制度や、墓じまいをする際の改葬手続きについてご紹介しました。
お寺で樹木葬を行う場合、必ずしも檀家になる必要はなく、檀家にならなくても戒名や法要の対応を受けられる場合があります。
寺院によって対応は異なるため、事前に確認しておきましょう。
後継者がいない場合でも安心して管理を任せられる霊園をお探しの場合は、「はなうたガーデン -伊東-」の樹木葬をご検討ください。
合同墓ではなく個別での区画をご用意していますので、自分だけの場所で自然に囲まれながらゆっくりと眠ることができます。
故人を大切に想う気持ちを尊重しながら、自分や家族に合った供養の形を選んでいきましょう。